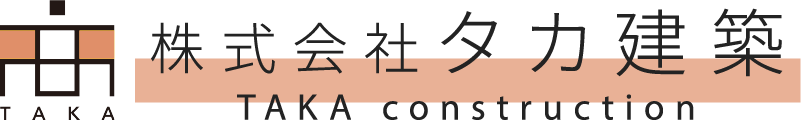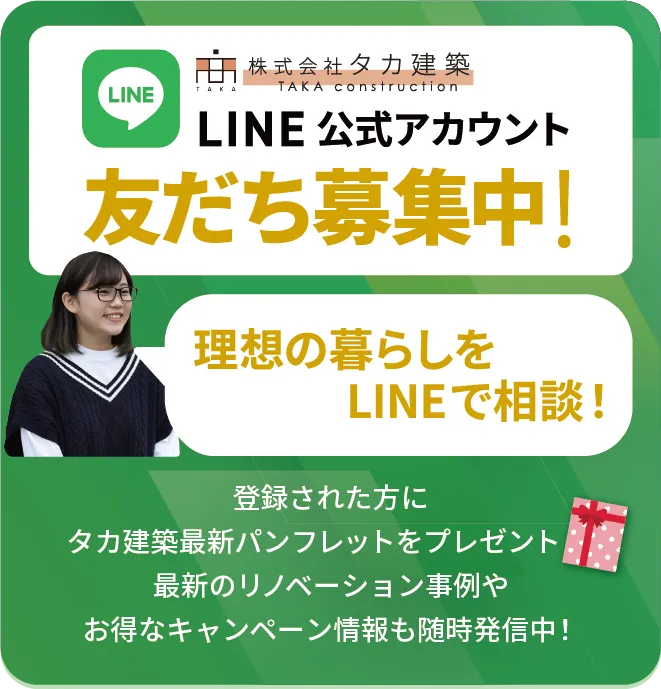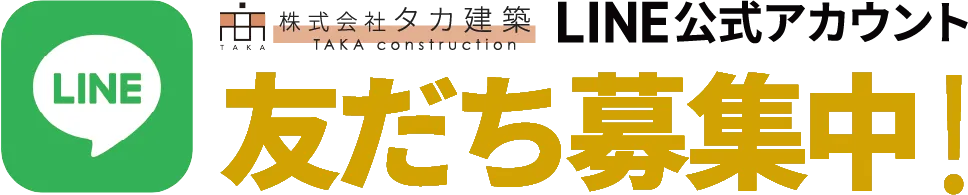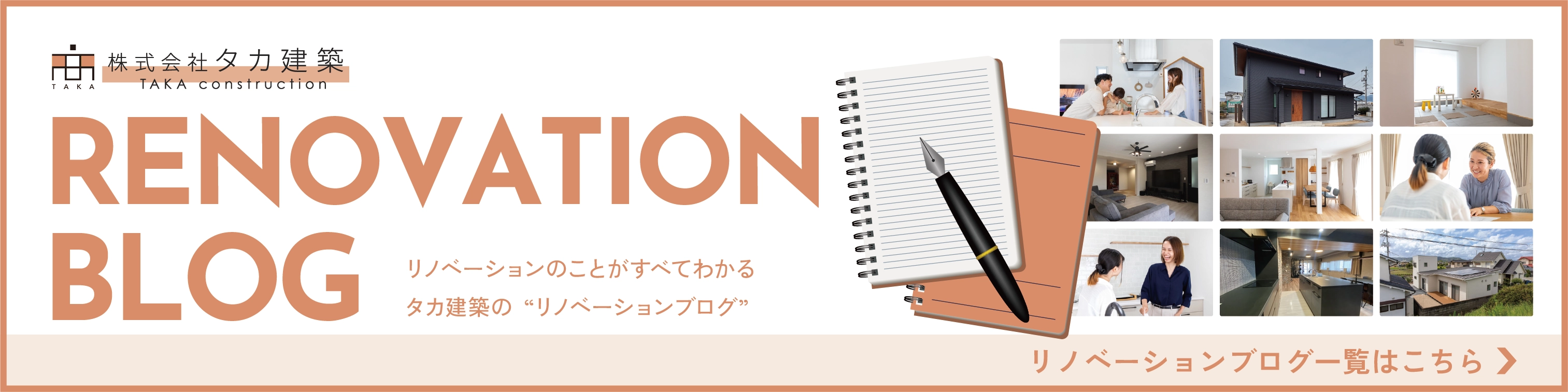“介護が必要になっても困らない家”はこうつくる|バリアフリーリノベ完全ガイド
|更新

日本は世界有数の長寿国として知られ、平均寿命は男女ともに80歳を超えています。超高齢社会の到来により、「人生の後半をどう快適に、そして安全に過ごすか」という問いは、今やすべての世代にとって無関係ではありません。特に、自宅での介護や老後の暮らしを見据えた住まいの準備として、「バリアフリー・介護対応のリノベーション」は近年、非常に注目を集めています。
バリアフリーとは、年齢や身体的条件にかかわらず、誰もが安心して生活できる環境を整えること。介護対応とは、日常生活でサポートが必要な人に対して、住まいの中でその支援がしやすくなるよう設計することです。どちらも、「住み慣れた家で、できるだけ長く、自立して暮らす」ための大きな鍵となります。
なぜ今「バリアフリーリノベーション」なのか?
高齢化にともない、以下のような現実的な課題が増えています。
- 加齢に伴う身体機能の低下(膝や腰の痛み、筋力の衰えなど)
- 室内での転倒事故の増加(特に段差や滑りやすい床が原因)
- 家族による在宅介護の必要性
- 介護施設ではなく自宅で最期まで過ごしたいという希望の高まり
これらを背景に、リノベーションを通じて住まいを“安全・安心な場所”に再設計する動きが活発になっています。また、国や自治体からの補助金制度も整備されつつあり、経済的にもリノベーションが現実的な選択肢となりつつあります。
バリアフリー・介護対応リノベーションの具体的な施策
バリアフリーリノベーションには、家全体を見直す大規模な改修から、特定の場所だけを改修する部分的なものまでさまざまなアプローチがあります。以下に主要な改善ポイントを紹介します。
段差の解消
- 室内の敷居をなくし、フラットな床に変更
- スロープ設置により、玄関や勝手口もバリアフリーに
- トイレや浴室への出入り口を引き戸にすることで、開閉の負担を軽減
手すりの設置
- 廊下、階段、トイレ、浴室などに手すりを設ける
- 握りやすさ・高さ・強度に配慮し、使いやすい位置に配置
床材の見直し
- 滑りにくく、クッション性のある床材へ交換(転倒時の衝撃を軽減)
- 車いす対応として、凹凸の少ないフローリングが人気
トイレの拡張・バリアフリー化
- 車いすでも入れるようにドア幅を広げ、回転スペースを確保
- 立ち座りしやすい高さの便座、L型手すりの設置
- 洗浄機能付き便座や非常呼び出しボタンの導入も有効
浴室の安全性向上
- 浴槽のまたぎ高さを低くし、入りやすくする
- すのこ床や滑り止め素材の床を採用
- シャワーチェアや昇降機の導入も検討の価値あり
照明とスイッチの工夫
- センサー式の照明や足元灯で夜間の移動をサポート
- スイッチやコンセントの位置を低めにして、座ったままでも操作可能に
介護者のための動線設計も重要

バリアフリーは高齢者本人のためだけでなく、介護を行う家族やヘルパーのための設計でもあります。特に以下の視点を取り入れることで、介護の負担軽減につながります。
- ベッド周辺に十分なスペースを取り、介護者が横につけるようにする
- 移動・移乗しやすい動線(トイレ・浴室との距離を短く)
- 折れ戸や引き戸で開閉の手間を最小限に
- 二重動線(介護者と家族がすれ違わないように通路を分ける)
介護が長期化する場合でも、これらの設計があることで精神的・肉体的な負担を軽減し、家庭全体のストレスが抑えられます。
補助金制度を活用しよう
バリアフリー・介護対応のリノベーションは、国や自治体の補助金・助成金制度を利用することで、自己負担を大幅に抑えることができます。
- 【介護保険制度】
要支援・要介護認定を受けた人が対象で、最大20万円(うち9割まで補助)の住宅改修費が支給されます。 - 【高齢者向け住宅改修助成(自治体独自)】
内容や金額は自治体により異なりますが、手すり設置や段差解消への助成制度が整備されている地域も多くあります。 - 【バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置】
条件を満たすことで一定期間、固定資産税が1/3減額される制度も存在します。
※最新の制度情報は、地域の市区町村窓口や厚生労働省のホームページ等で確認しましょう。
高齢の家族と暮らす住まいで大切にしたい工夫とは?

高齢の両親との同居や将来を見据えた二世帯住宅づくりでは、「安心して暮らせる動線」と「自分のペースを守れる空間づくり」が、住まい設計の重要なポイントになります。
以下のようなリノベーションの工夫を取り入れることで、親世代の暮らしがぐっと快適になるだけでなく、家族との距離も自然に縮まっていきます。
夜間も安心な寝室の配置と動線
高齢になると、夜間のトイレや移動の負担が増します。
そのため、寝室の位置はできるだけトイレの近くに設けるか、廊下動線を短くする設計が望まれます。
また、和室よりもベッド対応の洋室に変更することで、立ち座りや移動の負担も軽減され、夜間も安心して過ごすことができます。
段差のない床と連続した手すり設置
住宅内のわずかな段差も、高齢者にとっては転倒リスクにつながります。
廊下やトイレの段差をなくし、手すりを連続して設置することで、移動の際の安全性が大きく向上します。
特にトイレや浴室の出入口まわりには、手をかけられるポイントを複数用意しておくと安心です。
LDK内に“くつろぎスペース”を確保
日中、長時間ベッドに戻るほどではないけれど少し体を休めたい——
そんなニーズに応えるため、LDKの一角に小型のデイベッドやソファベンチを配置するのがおすすめです。
家族と同じ空間で過ごしながら、無理なく自分のペースで休める居場所があると、精神的にも安心感が生まれます。
高齢の家族が「自分の家」としてくつろげる設計を
こうした設計の工夫は、単に介護を意識した住まいというよりも、「自立をサポートしながら、尊厳を守る暮らし」をつくるためのリノベーションです。
家族が互いに気兼ねせず過ごせる関係を築くには、空間のつくり方が大きく影響します。
将来に向けて住まいを整える際には、ぜひ“使いやすさ”とともに、“心地よさ”も意識した設計を心がけてみてください。
まとめ:これからの住まいに求められるのは「やさしさの設計」
バリアフリー・介護対応のリノベーションは、高齢者のためだけでなく、小さな子ども、けがをした人、妊婦、誰にとってもやさしい設計につながります。一度リノベーションすれば、家はこれからの何十年を支える安心の場所になるのです。
「まだ元気だから」「介護はまだ先だから」と思っていても、住まいの備えは早ければ早いほど安心です。今のうちから、未来の暮らしを支える住まいづくりを始めてみてはいかがでしょうか?
![]()